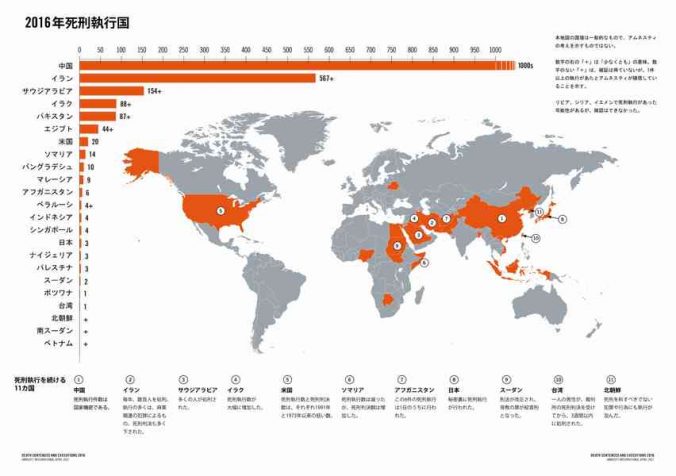無辜の保護という一点のみで、死刑廃止は正当化できる
袴田事件のようなえん罪事件では、死刑制度が決定的な問題として直ちに浮かび上がってくる。死刑が執行された場合、取り返しのつかないことになるからだ。未だに死刑制度を存置している日本は、果たして先進国の一員なのであろうか。世界の先進国とは、カネやモノをより多く持っているからなのか。そうではあるまい。人間の生命と尊厳に対して、国民の一人一人がどれだけの敬意を払い、それを社会的に保障しているか。その点を基準とするのが本当であろう。
2014年3月27日、再審開始決定で、袴田さんは釈放された。その翌日、駐日英国大使館はツイッターに、こう態度表明した。
「45年間にわたり死刑囚として収監されていた袴田さんが、証拠がねつ造された疑いがあるため、釈放されました。これは、司法が万能ではないこと、そして日本が 死刑 を廃止する必要性を示しています」。
イギリスでは、死刑執行後に真犯人が発覚した「エヴァンス事件」という冤罪事件をきっかけに死刑廃止の機運が高まった。1960年代に反逆罪など一部の犯罪を除いて死刑が廃止され、1998年に完全な死刑廃止に至っている。
この英国大使館の日本へのメッセージは、日本という独立国家の主権を侵害するものではない。我々は、日本国民である前に人類(世界)の一員である。日本の生活と文化をその基盤として支えている世界的な文明の恩恵を享受している。国によって文化の違いは認められて当然であるが、人間の自由、平等、尊厳を保護するという社会の底流にある文明の素について、イギリスには当てはまるが、日本人にはなじまないなどというものではない。世界文明のキーストーンとしての人権尊重の思想は、人類社会において普遍性を備えている。
死刑は、不可逆的で絶対的な刑罰である。元の生きている状態に戻すことはできない。また、「身体刑」の究極であって、切り落とす身体部分を腕一本にするか、そこに足一本を付け足すかという相対勘定も入り込めない。また、死刑は人体に直接襲いかかるばかりではない。死刑を前にして、迫りくる絞首刑を想像することが耐えられない苦しみを与える。判決が出されてから執行されるまで、死刑囚を四六時中脅かしているのだ。
捜査官も裁判官も、人間である以上間違いを犯すことがある。裁判では「真実」を確実に発見するという保証はなく、誰がやってもどこまで行っても冤罪の危険性から自由ではない。刑事司法の法体系には、再審制度がその中でレギュラーポジションを占めている。それも近代が始まるのと軌を一にした歴史をもち、日本も採用する英米法では、無辜の救済のみを目的としている。確定判決を受けた者の利益のためにのみ再審が認められるのだ。最近、再審請求中であるにも拘わらず死刑執行が相次いでいるが、それでは無法状態ではないか。もとより、万が一の間違いから人の命を守るためには、社会のルールとしての死刑はあってはならない。無辜の生命を保護するためには、明らかに有罪と判ずることができる場合であっても、死刑は排除すべきである。「疑わしきは、被告人の利益に」「10人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰してはならない」という刑事司法の原則を徹底させなければならない。法体系から死刑をなくすことは、無辜の保護という一点のみでも正当化される。
袴田事件だけではなく、実際のえん罪事件の裁判を覗くと、酷くレベルが低い。「こんなことも認められないのか」「それはないだろう」ばかり。裁判において、検察官の牽強付会ぶり、また、裁判官の「自由心証主義」という名のもとでのコジツケとその強弁に対して、「誰にでも簡単にわかることを認めてもらう」のが裁判での弁護側立証だと言われるほどである。
さらに、逮捕から公判に至るまで無実を主張し続けると、「反省がなく、情状酌量の余地がない」と勝手に判断され、死刑判決が出るケースが多い。なんと、「推定無罪」ではなく「推定有罪」がまかり通り、屁理屈で武装したえん罪事件の死刑判決がこれまで続いてきた。そして今後も繰り返されていくことが予測される以上、極刑である死刑の存置を決して許してはならないと考える。
死刑は公務員による野蛮で残虐な刑罰である
死刑制度は廃止されなければならない。何故なら、野蛮で残虐に過ぎる刑罰だから。
日本国憲法には、こう規定されている。
第三十六条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
ここで言う残虐な刑罰とは何を指すのか?死刑以外にはない。従って、日本国憲法が施行されると同時に、死刑制度は廃止されなければならなかったのだ。
憲法九条では、国の交戦権を否定している。要するに、国家が戦争で外国人を殺してはならないということを命じている。国家権力の発動として、外国人は殺してはいけないのに日本人を殺して良いはずはない。「善人」であろうが「悪人」であろうが、誰に対しても国家権力は殺人のライセンスなど持ってはいないのである。
死刑とは、人権侵害の究極である。自然権としての人権とは、どんな法律にも規制されず、どんな契約にも縛られない。国家、法律、契約などに絶対的優先権を持つ。自然に備わっている天賦の権利が人権なのである。刑法に死刑を取り入れても、本来それは無効である。そして、死刑の存廃は多数決で決める課題でもあり得ない。
日本で採用している死刑は絞首刑である。絞首刑の残虐性が裁判で争われたことは、何度かある。いずれのケースでも、「絞首刑は憲法36条にいう残虐な刑罰ではない」との最高裁判所の確定判決(死刑制度合憲判決事件)が出ている。
ならば、実際の死刑がどのくらい残虐なのか、証言を求めよう。
「処刑された遺体から目と舌が飛び出ていて、口や鼻から血液や吐しゃ物が流れ出し、下半身から排せつ物が垂れ流しの状態だった。」
「ロープにこすられて顔から肉がもぎ取られ、首は半ばちぎれていた。」
次は、明治時代の記録で、小野澤おとわという人物の絞首刑執行である。
「刑台の踏み板を外すと均(ひと)しくおとわの体は首を縊(くく)りて一丈(いちじょう)余(よ)の高き処(ところ)よりズドンと釣り下りし処、同人の肥満にて身体(からだ)の重かりし故か釣り下る機会(はずみ)に首が半分ほど引き切れたれば血潮が四方あたりへ迸(ほとばし)り、五分間ほどにて全く絶命した」「絞縄(しめなわ)のくい入りてとれざる故、刃物を以て切断し直に棺におさめた」
このくらいで吐き気を催すから止めておく。日本と同じく死刑存置国のアメリカでは、絞首刑は非人道的とされ、残虐性を薄めようと努めている。絞首刑から電気椅子での刑になり、今では薬殺刑が主に選択されている。絞首刑は失敗することがあって、凄惨な事態を経験したからだという。
世界各国で実行されている死刑の種類を記し、想像力を働かせるための参考に供したい。
絞首刑(つるし首)、電気刑(電気椅子)、ガス殺刑、銃殺刑、斬首刑(首を切り落とす)、石打刑。イランや北朝鮮では、刑の執行を公開している。歴史を振り返ると、さらに残虐な方法がある。拷問の歴史もそうだが、死刑の歴史は酸鼻を極める。
絞首刑、斬首刑、鋸挽き、生き埋め、十字架刑、溺死による処刑、薬殺刑、杭打刑、串刺し刑、磔刑、腰斬刑、皮剥ぎの刑、腹裂きの刑、凌遅刑、石打ち刑、火刑、釜茹で、銃殺刑、突き落とし、車輪刑、電気椅子、炮烙、圧死刑、四つ裂き刑)、八つ裂きの刑、猛獣の餌食等。
かつて、我々の祖先はかような残忍非道 に手を染め、あるいはその手にかかってきた。現代でも、報復感情が爆発するとこのような狂った罰を欲することがあるから恐ろしい。人間以外の動物の世界に殺し合い(死刑)はない。傲慢にも、人間は非道に対して「ケダモノ!」と罵るが、実は人間はケダモノ以下なのではないか。
死刑は応報。威嚇効果、隔離効果もある。だから良いのか
かつて、死刑がのさばっていたころ、「刑罰は、悪に対して悪をもって対抗する悪反動であるため、犯した犯罪に相当する刑罰によって犯罪を相殺しなければならない」という絶対的な応報が唱えられていた。死刑を理論的に正当化するための刑罰応報論である。だが、放火による殺人には火あぶりの刑を、刺殺の場合には磔刑(磔(はりつけ)にして刺し殺す刑)を、というように、そこまで具体的に対応させてきたわけではない。「殺人には殺人を」ということである。この相殺論では、殺人以外の罪に対して死刑というわけにはいかない。
1948年の最高裁判例では、「犯罪者に対する威嚇効果と無力化効果(隔離効果)による予防説に基づいて合憲」としており、応報刑的要素についての合憲性は排除されている。犯罪者(予備群)に対する威嚇だというが、そうではない。すべての国民に対する威嚇である。もう一つの理由として、犯罪の無力化効果(隔離効果)というが、刑務所に隔離すれば済むこと、何も抹殺までしてあの世に隔離する必要はないではないか。結局のところ、威嚇、脅し。それで凶悪犯罪を予防するというのである。いずれにしろ、野蛮な考え方で、人間の尊厳や生命の価値を基本原則としての論ではない。
死刑が威嚇なら、刑罰全般もそういうことになる。法を犯して社会秩序を乱すと酷い目に合わせるぞ。そんな、脅しで泰平の社会を築こうなどという発想が野蛮ではないか。そういう野蛮で未開な次元から脱却しようとしてきたのが、近代、現代の歴史ではないのか。歴史の進歩とは人口と物が増え生活が便利になっただけではなかろう。圧政との闘いの歴史の行きつく先がこれか。脅されて汲々と暮らすのが理想であったのか。人生を歩む旅人として、北風に曝されるよりも太陽の陽射しを浴びて外套を脱ぎたいものだ。
ここで、冤罪に関わることを思いだす。罪を犯してもいない被告には濡れ衣を証明する手立てはごく限られている。気力だけでは、どうしようもない。だが、被告の生命を手中に握る人たちが死刑にするのに冒す危険といえば、度々やってしまう思い違いだけ。判決で死刑判決を出し、それが過誤であったことが分かっても、何ら罰せられることがないのはどういうわけだろうか。死刑判決に関わった人たちはみんな殺人の共同正犯ではないか。細かいことを云えば、職権の濫用もある。証拠をねつ造した捜査官、それを利用して死刑を求めた検察官、死刑を決定した裁判官の責任はどうなるのだ。被告が冤罪を晴らしても、人生は元に戻らない。えん罪を作った方は、お咎めなしで出世街道を歩き続けるというのは、不公平極まりない。「死には死」ではないのか。そう言いたいところではあるが、人間の命にこんなに著しい軽重があるのは誰しも大いなる不満を禁じ得ないだろう。
しかも、過って無辜を殺してしまう罪だけではない。真犯人を逃がしてしまっている。その罪が付け加わることを忘れてはならない。無辜を罰してはならないと言いながら殺し、真犯人を逃がしてしまうこの二重の罪は、新聞にも雑誌にも載らない、テレビにも流れない。誰も指摘することなく、当たり前のようになっている現状には、戦慄を覚えずにはいられない。せめて、人智が万能ではないのであるならば、「99人の真犯人を逃しても、1人の無辜を罰してはならない」原則を絶対的に厳守すべきである。
被害者遺族の感情はどうなるのか
裁判の実務では、応報論は生きている。犯行の被害の程度を考慮して量刑が行われている。また、「被害者家族の被害はどうやって埋められるのだ。死んでお詫びすべきだ」。死刑肯定論者の感情的にして強力な主張も、応報論である。自分の親兄弟、妻子が殺人事件の犠牲者であったら、その犯人を死刑にせずにはおかないでしょ、と言われる。被害者感情を重視せよ、と言う声が最近とみに大きくなってきている。
被害者の遺族の気持ちを考えてみよという心情は理解できる。では、身寄りのない被害者の場合は、遺族がいないので死刑でなくとも良いのか。遺族の悲しみといっても複雑。我が子や親、親族に対する殺人(尊属殺人)は、殺人事件全体の4割以上を占める。心中事件で死ぬケースを入れるともっと増える。その場合、遺族はストレートに死刑を望むのか。そんなことはない。復讐するとなどと考えもしない。被害者も加害者も身内なのだから、その思いは複雑極まりないのではないか。
被害者遺族の感情を重視するという点で、外国に例がある。イスラム法国家では、被害者遺族が赦した場合は死刑執行が免除されるというコーランの教えがある。また、アメリカでは被害者遺族が死刑を望まない場合は、知事が死刑を終身刑に減刑することが可能である。これらの例は、遺族の思いを考慮して量刑を緩和するケースであって、日本で言われているような遺族に代わって刑を重くするわけではないのである。
日本では被害者遺族が法務省に死刑執行を止めるよう求めても、それが考慮されることはない。遺族の思いとは関係なく処刑している。あるいは、裁判で死刑判決を求めても、遺族の要求だからといってそのまま受け入れられてはいない。すべての事件に被害者遺族がいるわけでもなく、遺族がいてもそのすべてが死刑を期待するわけでもない。また、死刑の執行で遺族の感情が回復し元に戻るなら一考の価値があるかもしれないが、大切な肉親の喪失感を打ち消すことは到底無理であろう。それは完全に解決されることはないが、死刑制度とは別に社会全体の問題として対策すべきではないか
現実の死刑はどうなっているのか。最近の殺人事件被害者数、死刑判決確定者数、その総数(執行されていない数)、死刑を執行された数は、下記の表の通り。
| 日本の死刑 | 確定者数 | 確定者総数 | 被執行者数 | 殺人事件被害者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2010(H22) | 9 | 111 | 2 | 465 |
| 2011(H23) | 23 | 131 | 0 | 442 |
| 2012(H24) | 9 | 133 | 7 | 429 |
| 2013(H25) | 8 | 130 | 8 | 370 |
| 2014(H26) | 6 | 129 | 3 | 395 |
| 2015(H27) | 4 | 126 | 3 | 363 |
| 2016(H28) | 3 | 129 | 3 | 289 |
被害者数は警視庁調べ(犯罪情勢)、以外はアムネスティ調べ
死刑判決を受けるのは、殺人事件の中でも凶悪で、情状酌量の余地がない事件だけ。刑が確定するのはわずかであることがわかる。処刑数も実際にはわずかな数字なので、その痛みが社会に広がっていくこともない。威嚇の効果も知れたものである。
「死には死」とすれば、社会は一体どうなってしまうのか
「誰かを死に追いやったなら死をもって償うべき」という死刑肯定論は、一見反論しにくいと思われるが、この考え方は実に危険。社会を破壊するほど危険である。血で血を贖う死刑制度は社会を残虐に堕落させてしまう。人々の心に戦慄が走り、精神を委縮させたり、狂わせるに違いない。
極端な話をしよう。「死には死」としたらどうなるか、考えてみていただきたい。故意、過失を問わず自分が原因で誰かが死ぬということならば、交通事故や医療事故、過誤による死も当てはまる。交通事故では、年間数千人が命を落とす。これらを殺人事件での死者に加えるとさらに多い数に膨れ上がる。年間に死刑囚が数千人の規模で増えていく。それだけの人数を収容しきれないので、直ちに死刑執行となる。
毎年、数千の絞首刑が執行される。そうなると、死刑の「犯罪抑止効果」、威嚇効果を上げるためには、死刑をより残虐にしかも公開で執行すればよい。そうすれば犯罪が効果的に減少し、死刑囚の数も減るという悪魔のささやきが現実味を帯びてくる。そうするとどうなるか。
1年間で数千人の死刑を誰でも見学できる公開の場所で執行する。それも。全国の刑場を10カ所とし、数千人を処理。各地で毎日2人づつの絞首刑。あるいは毎月まとめると、月に40人くらいづつ一気に処刑されるのである。毎年、数千人ずつ人口が減っていく。否、殺人や事故で数千人が死ぬのだから、合計で一万有余の人命が失われる。さらに想像力を羽ばたかせると、それだけではない。一万有余の人には家族親戚、友人知人がいる。当然彼らも平気ではいられない。数万、数十万、数百万の辛酸をなめる被害者、夥しい犠牲が都市や田園を走り、日本中を覆うのだ。文明社会は崩壊しないだろうか。
確かに犯罪は減るかもしれない。が、どうだろう、その凄惨な光景は。未来社会の荒ぶる姿を、暴力が支配する社会としていち早く描き出すハリウッド映画の場面が浮かぶ。この原点は「命には命で贖う」ということだ。同時に、平和で自由な社会、人間の尊厳は死ぬことであろう。これでいいのか。よさこい祭りよりも頻繁に絞首刑が公開で実行される結末、その地獄絵図は果てしない。
こんな社会をあなたは望むのか。こんな残虐でも平気でいられるのか。見ている子供たちは絞首刑の真似をし始め、大人たちはこんな日常にうんざりすることだろう。年配者は、「こんな社会を作ってきた覚えはない」と嘆き恐れおののくに違いない。「命には命」の論理を単純に突き詰めると、こんな風に社会が残酷に狂い死んでしまうのである。私は、そんな悪夢にうなされるのである。
日本では、「死をもって贖う」のが慣習であった、などと言う言説もある。これは見当違いも甚だしい論。古の日本には死罪はなかった。実に平和な社会であった。極刑は遠島(島流し)。酷い目にあわされた人は死んで祟ると信じられていたからである。「祟り」の信仰によって死罪を避けていた。また、不殺生を説く仏教の教えの影響もあった。そこへ残虐さを持ち込んだのは武士であった。
歴史の時代によって死罪の有無やその形態も変わってきた。が、言えるのは、日本人は残虐さを避ける平和的な民族だったということ。「死をもって贖う」のが古来よりの醇風美俗だという人はきっと、神風特攻隊や人間魚雷回天(一人乗りで爆薬を積み、敵艦に体当たりした特攻潜水艇)、そして震洋(爆弾を積んで体当たりするベニヤ板製のボート)での攻撃を「お国のため」と称して礼賛する人でもあると思う。人権意識ゼロだからである。
さらに言おう。
被害者感情をどうしてくれる、裁判でも被害者遺族の意見を取り入れ遺族の感情に報いるようにしろ。あなたは自分の妻子が殺されたらどう思うか。犯人に死刑を望むことだろう。犯人を許せるか、考えてみろ。と、その興奮は留まることがない。
そう、誰しも自分の家族や親友が殺されたら冷静ではいられない。応報感情を抑えられない。だから、だから。冷静ではいられないから、犯人捜査や刑事司法に関わってはいけないのだ。公正さを担保するために、当事者または当事者に準ずる者はその件に関わることなかれ、というのは民主主義社会の原則。当事者以外の第三者が冷静に問題解決に当たるべきである。
例えば、警察官の子供が事件の被害者となった場合、その警察官はその事件の捜査からは外される。裁判官は自分の家族が関わる刑事事件であれ民事事件であれ、その事件を担当することはない。何故ならば、冷静な捜査や公平な判断ができないからだ。それは人情の暴走から社会を防衛するための知恵なのである。刑事司法に被害者、加害者、その関係者が立ち入って影響を与えるのはタブー。この原則は、現代社会では誰しもが認める常識と言っていい。
付け加えれば、事件の捜査に始まり、公判、刑の執行に至るまでの刑事司法は、かたき討ちではない。リンチ(私刑)でもない。被害者に代わって国家が加害者に報復するわけでもない。私的であれ公的であれ、報復は報復を呼び、復讐の連鎖をもたらす。しかも報復と言っても復讐と言っても良いが、必ず拡大再生産されていく。行きつく先は自滅である。歴史を紐解けば、その事例に事欠くことはない。
国家に国民の生命を与奪する権利はない
「報復としての死刑」や「見せしめとしての死刑」は、歴史的に死に絶えることなく現役で制度化されている国が残っている。しかし、現代史の流れは死刑制度廃止。国連総会は、1989年12月、死刑廃止を目的とする議定書(死刑廃止条約)を採択。その議定書第1条では「本議定書の締約国の領域において、何人も死刑に処せられない。各締約国はその領域内における死刑廃止のため全ての必要な措置をとる」と明確に宣言している。それ以降、野蛮で残虐な死刑を廃止する国が増えてきている。
それは、第二次世界大戦の終結後、7千万人近い犠牲者(直接の死者)を出し国土を焦土と化した惨状を目の当たりにして、人権思想が市民権を獲得して広く周知されてきたからだ。刑罰に関する考え方が転換された。罪を犯した者に対して、苦役を課して(痛めつけて)思い知らせるというのが刑罰。また、犯罪者は社会から隔離して社会を防衛する。そうすることで、社会の秩序を保とうとする。これは非人道的な古い考え方で、ベクトルが戦争と同じ方向、残虐さに向いている。
人間の尊厳は全てに優先する。第二次世界大戦以降の世界は、日本からすると日中戦争と太平洋戦争に負けてアメリカ軍に支配された以降のことだ。世界は、「二度ど戦禍を招かない」と決意した。その原点で社会を再起動させ、人権思想を実現にするべく社会制度の最適化を図ってきた。世界人権宣言に続く日本国憲法がその象徴なのである。
現在、欧州連合 (EU) 各国は、不必要かつ非人道的であることを理由として死刑廃止を決定し、死刑廃止をEUへの加盟条件の1つとしている。欧州議会の欧州審議会議員会議は2001年6月25日に日本およびアメリカ合衆国に対して死刑囚の待遇改善および適用改善を要求する1253決議を可決した。この決議で日本に対して、死刑の密行主義と過酷な拘禁状態を指摘している。
第69回国際連合総では、2014年12月18日、「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が、過去最高数に達する117カ国の賛成により採択された。死刑制度を存置する国々に対し、死刑に直面する者の権利を保障する国際的な保障措置を尊重し、死刑が科される可能性がある犯罪の数を削減し、死刑の廃止を視野にまずは死刑執行を停止することを要請する決議である。
しかし、日本政府は、過去5回の死刑廃止、執行停止決議のいずれにも反対している。賛成国は増える一方であるにも拘らず、反対票を投じ、決議をあざ笑うかのように処刑を断行した。明らかに死刑廃止という世界の動きに逆行。さらに、国連自由権規約委員会の第6回日本政府報告書審査において、日本政府はあらためて、死刑制度の廃止を含む勧告を受けた。日本政府は死刑を廃止しない理由として「国民の大多数が死刑を支持している」からといって、国連などからの勧告に従わないでいる。死刑制度は、もとより多数決で決めるものではない。国民が「拷問や残虐な刑罰」を致し方ないとして認めれば、それらの行為は許されるとでも言うのか。そんなことはない。国民の世論に対して憲法の規定は優先する。ましてや、憲法に先立つのが自然権としての人権なのだ。
48年間被告が拘束され続けた袴田事件は、えん罪の可能性が高い判決として国際的に注目された。昼夜独居処遇による収容体制の見直し、情報の十分な開示、死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度の確立、および拷問等による自白の証拠不採用など、国連の委員会は厳しい勧告を出した。
いかがわしい世論調査、8割以上が死刑賛成って本当か
2004年に内閣府が実施した死刑制度への賛否調査「基本的法制度に関する世論調査」では、死刑に賛成が8割を超えていたという結果が出ている。しかし、世論調査というものには、必ず「誘導」がある。主催者の意向に沿うような結論が出るように、質問の仕方を工夫する。この調査でもそう。「場合によっては死刑もやむを得ない」という選択肢があった。こう訊かれれば、たいていの人は肯定してしまう。随分とバイアスがかかった質問である。この仕組まれた罠にはまった人が、8割を超えたということなのである。質問の向きを変えれば、結果はまったく異なったものになるに違いない。 世論調査で死刑賛成派がいかに多くとも、人間の生存権を否定することはできない。繰り返すが、世論調査で死刑賛成派がいかに多くとも、世論によって人間の生存権を否定することはできない。世論が侵略戦争を支持すれば、隣国に攻め込んでよいのだろうか?世論が認めれば、拷問が奨励されるのだろうか?世論といえども、人間の自由と尊厳を否定することはできない。従って、死刑制度の存置がそれで認められるわけではないことをお断りした上で、その世論調査を検討してみる。
調査の結果は、「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」が6%。「場合によってはやむを得ない」が81.4%。「わからない、一概には言えない」が12.5%であった。ところが、「場合によってはやむをえない」の回答者にさらに聞くと、「将来も死刑を廃止しない」が61.7%、「状況が変われば、将来的には死刑を廃止しても良い」が31.8%、「わからない」6.5%と出た。
この結果を、死刑存置論者は8割以上と言えるのか。「場合によってはやむをえない」の中の「将来も死刑あり」が6割なのだから、本当の死刑存置論者は、全体の約半数というところが実際である。質問の仕方で誘導し、さら恣意的に結果を分析した結果が8割。この「結果」を宣伝することで世論を舵取りしようという意図がうかがわれるのだ。「みんなそう言っている」となれば、世論の流れは加速するのが日本人の風潮であるからして、この宣伝は効く。だが、心の底まで変えることはできないのではないか。太平洋戦争で「天皇陛下万歳」と心から叫んで死んでいった兵士は、本当に多数なのか、疑問である。日本人の表面的な浅薄が言われるが、私はそれを信じてはいない。
現在ではこのキャンペーンが浸透した結果、8割の国民が死刑制度を肯定的に捉えているかもしれない。恐ろしいことである。近年、凶悪犯罪は統計的には減少しているにもかかわらず、厳罰化の傾向にある。マスコミの報道姿勢が操っている。新聞や雑誌は「酷いことが起こっているぞう」と騒ぎ立てた方が売れるから。「悪い奴には人権などない。人ではないのだから、何をやってもいいのだ」などと嵩にかかっている人も目につくようになった。
その手の人は、米軍が広島、長崎に原子爆弾を落として数十万人を虐殺し、何百万人の負傷者、その家族、親戚、友人を犠牲者として残した凄惨な事件に対して、「犠牲者の気持ちになってみろ」「やられたんだかから、やり返せ」といきり立ってもよさそうだが。8割の死刑肯定派であっても、アメリカに報復する原子爆弾の必要性を説く人は皆無である。実のところ、アメリカが強いから「報復」できないとすれば、「死刑」は弱い者いじめと言う外ない。
理性的に考えれば、報復を肯定することはできまい。だから、原爆を抱えてアメリカに向かっていかなくても良い。「ヒロシマ、ナガサキ」の被爆経験から、日本は、そして世界は、絶対的な平和を希求した。人の命の尊さを、命をいともたやすく奪って憚らない暴力の凄まじい恐ろしさを知った。その実感と考え方を、市民社会になお残されている中世の名残りとしての死刑制度にも適用すべきなのである。死刑制度をどう考えるかは、その社会の文明度を表示する。日本国民は、そのことにいち早く気が付かなければならない。
死刑制度は、一日も早く廃止されるべきである。