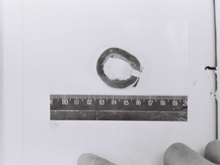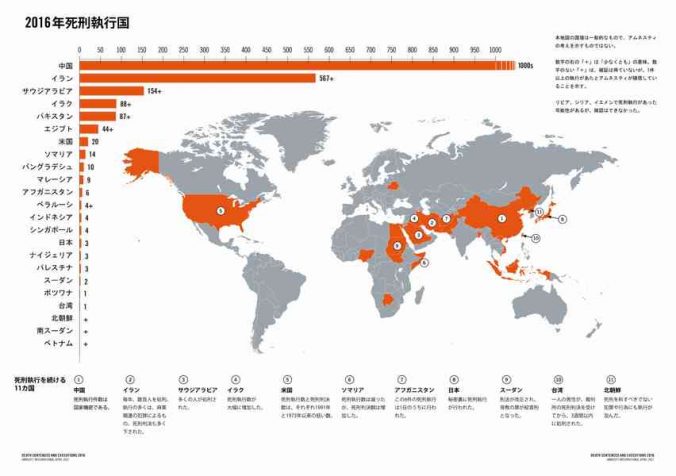有罪証拠の柱・『5点の衣類』は、ねつ造
袴田事件最大の争点『5点の衣類』とは?
『5点の衣類』とは、事件から1年2か月後に発見された5点の衣類の事です。 それはズボン、スポーツシャツ、ステテコ、半袖シャツ、ブリーフの5点で、事件のあった 味噌会社の専務宅から線路を隔てた味噌工場の深いタンクの底から麻袋に包まれた姿で発見されました。

ステテコ

鉄紺色ズボン

半袖シャツ

スポーツシャツ

緑色パンツ
公判開始から1年が過ぎ、パジャマ以外物証がなく検察の立証は完全に行き詰っていた時のハップニングでした。起訴状にはない重要証拠が突然出現しました。検察はすぐさま訴因を変更、起訴状や「自白調書」に反する主張に乗り換えたのです。
拘置所にいた袴田さんは、これを「真犯人が動き出した証拠で、ますます有利になりました」と、大喜びで母親に手紙を書いています。無実の被告人としては、『5点の衣類』がまさか自分に着せられる濡れ衣だとは思いもよらなかったことでしょう。
弁護団は異例の展開に十分反論できないまま、68年9月『5点の衣類』を最大の決め手に死刑判決が下されました。確定控訴審(東京高裁)の審理においても、5点の衣類を中心的な証拠として死刑判決が維持されました。以降、『5点の衣類』が犯行着衣でしかも袴田さんのものなのか、この点が裁判の主要な争点となってきたのです。
誰もが事件との関連を容易に想像できる場所にあえて隠す理由は何だったのか?発見の経緯が謎だらけで、袴田さんと結び付けるために様々な細工も施されていました。同僚の会社員なら袴田さんをすぐに連想できるステテコと緑色ブリーフ。そしてズボン、スポーツシャツ、半そでシャツには袴田さんの「自供に合わせる」かのように損傷が作られていたのです。しかも5点の衣類にはすぐそれと分かる大量の血が付着しており、警察は衣類発見からすぐに『5点の衣類』を犯行着衣と決めつけ、異例のスピードで審理が進められました。
いつ、誰が、何故、深さ1,67mもの巨大な味噌タンクの底に隠したのか?謎は深まるばかりですが、見方を変えて誰かが袴田さんを犯人にするために仕組んだ罠だとすれば謎が解けるのです.

マッチと絆創膏
実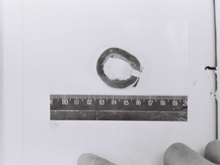 はこの時、味噌タンクから発見されたのは『5点』だけではなかったのです。
はこの時、味噌タンクから発見されたのは『5点』だけではなかったのです。
衣類の損傷は常識では考えられないほどずさんな物でしたが、注目すべきは味噌タンクから見つかったのは5点の衣類だけではなく、ズボンの左後ポケットに「こがね味噌」の名入りマッチと絆創膏が入っていたことです。袴田さんは消火作業中に左中指に深い切り傷を負っていて、警察はもちろんそのことを知っています。会社名入りのマッチも犯人がこがね味噌会社の関係者であることを暗示する見えすいた小細工です。犯人を特定する証拠を残すこと自体、隠すという行為とは相反しています。しかも、袴田さんが負傷したのは左中指なので絆創膏は右手に持って治療します。治療が終わり、右手でポケットにしまうなら常識的には右後のポケットです。警察はそこまで頭が回らなかったのでしょう。不自然というより全てがありえない事です。
謎だらけの『5点の衣類』
【発見の経緯】
事件発生から1年2ケ月後の1967年8月31日午後4時過ぎ、『こがね味噌』工場内にある『一号タンク』から赤味噌の搬出作業をしていた従業員が異物の混入に気づき、掘り出してみると南京袋でした。「袋の口は縛ってなくて、中に手を突っ込むと衣服が入っていた。つかんで取り出したらこれが血に染まっていた」「素人が見ても血だと分かりました」第17回公判(1967/9/13)での従業員Mの証言
味噌タンクは縦横約2mのほぼ正方形、深さ167cmで地上部分は91cmあり、南京袋はタンクの底の底、縁から165cmの所で見つかった。この時点で1年前に仕込まれた8トンの味噌は大方出荷されていて、事件直後とほぼ同量の味噌が入っていたところでした。しかし、味噌工場は事件直後に警察の捜査が入り厳重に調べられていたところでした。見落とすことなど考えられない捜査があった場所
誰が、いつ、隠したのか?
一審の静岡地裁の判決では「味噌タンクに隠した状況、日時は全く根拠がない」としたのが東京高裁では「7月20日以前、それ以降は不可能」と変わり何の根拠も示さず断定し、犯行着衣であるとされてしまいました。弁護団もこの時点ではまさか警察がねつ造するとは考えられなかったのです。

味噌タンク(発見場所)
【衣類の疑問】
―ありえない服装と不自然な衣類の損傷からずさんなねつ造が見えてくる―
事件当日は台風一過の熱帯夜(新聞発表によるとこの日の旧清水市の気温は28℃,湿度80%)。84歳の今、いつも扇子を手放さない無類の汗かきの袴田さんが、緑色パンツの上にステテコをはき、さらに秋冬物の純毛製の厚いズボンをはいて、上にはメリヤス製の半袖シャツにアクリル製の長袖のスポーツシャツという服装で、4人を相手に大立ち回りをしたことになります。「自供」によれば、さらにこの上に厚手のゴム雨合羽を着て、ゴムサンダルを履いて、専務宅へ侵入するため、木によじ登ったというのです。
これはもう笑い話です。真冬の街歩きにも扇子を手放さず、汗びっしょりになる袴田さんの今が無実を証明しています。ステテコは男性にとって夏の部屋着の様なもので、普通ズボンの下にパンツと一緒にはくことはまずありえません。汗かきの袴田さんならなおさらです。
また、着る必要のない雨合羽と血が全く付着してないゴムサンダルについては、袴田さんの無罪の証拠だから検察は触れなくなりました。
【犯行着衣らしく見せること】
5点の衣類が犯行着衣であるかどうかと袴田さんの物であるかということは本来別の問題なのですが、警察にとってねつ造の目的は、5点の衣類が犯行着衣であるかのように見せることであり、さらに5点の衣類が袴田さんの物だと立証することでした。
そのために袴田さんを連想させる緑色パンツとステテコは必要不可欠で、シャツとズボンには自供に添った損傷があることが重要だったのです。袴田さんの犯行というシナリオ自体が空想の産物である限り、想像だけで完壁にねつ造するのは不可能で、付着した血が上着より下着の方が多いとか、右肩の傷とシャツの損傷の位置も数も不一致なこと、すねの傷とズボンの損傷の鍵型の向きが逆だったこと等々、全て杜撰(ずさん)です。
第一次再審での静岡大学沢渡教授の鑑定では身体の傷と衣服の損傷、血痕の位置には法則があり、半袖シャツはその法則に反している。半袖シャツとスポーツシャツがねつ造されたもので、別々に傷が付けられたとすればこのような食い違いが生じたことは理解できると証言しています。
事後のねつ造ですから、シャツとズボンの損傷が袴田さんの生身の傷の位置と厳密に合致させることは不可能。おそらく、犯行着衣らしく見せれば、後は裁判所が上手に言い繕ってくれるだろうとの期待があったでしょうし、裁判はその思惑通りに進んできました。第二次再審の静岡地裁決定で、ウソが見破られるまでは。
【なぜ5点なのか】 ―ねつ造の意図が透けて見える―
ふつう犯人が犯行着衣を処分する時、確実に発見されそうな場所に、殺人の決定的証拠を隠すだろうか。発見させるためなら理解できる。工場のすぐ外は海岸線が続いており、スコップと麻袋を抱え、ハシゴで深い味噌タンクの底に降りて行く危険よりも、海に投棄する方がはるかに安全だ。また、味噌タンクのそばのボイラー室で、あるいは放火したときに一緒にしてすべて焼却すれば簡単に始末できます。
しかも、残虐な強盗殺人放火事件の関係証拠が、なぜ5点だけなのかという疑問も当然湧いてきます。それはねつ造する側の事情によって『5点』が《必要十分》だったと考えるのが自然です。袴田さんのものと思わせるためならブリーフとステテコだけで《十分》だったのに、犯行着衣に見せるためには、自供に沿うような傷が付き、血染めになった半袖シャツ、スポーツシャツ、ズボンが《必要》だったのです。
重大なことに、ここに袴田さんのものであるパジャマとゴムサンダル(犯行時に身に着けていたとされた証拠物件)が入っていない。別に見つけている。特にパジャマは決定的な証拠として扱われていました。そのことは、5点の衣類は事件と関係がないことを示唆しています。もし、真犯人が犯行着衣を隠すならば、最初に犯行着衣とされたパジャマやベルト、手拭い、ゴムサンダルなど事件現場で血がついて発見されたとされたもの全てを一緒に処分するでしょう。血染めの衣類とこれらの付属物も証拠価値としては同等で、処分し忘れることは真犯人にとって致命的なミスにつながります。静岡県警が知恵を絞って考え、選別した結果が『5点』だったのです。5点の衣類は袴田さんの物かどうか疑わしいものばかりで、一緒に入れられなかったパジャマとゴムサンダルは間違いなく袴田さんの物であり、無実の証拠だからです。誰でもねつ造できる『5点』だということが、ねつ造の証拠なのです。そう考えれば、ズボンのポケットにマッチと絆創膏がこれ見よがしに入っていたことが理解できます。
裁判所はどう評価・判断したか
確定判決(1976.5.18)の認定
㋐5点の衣類には下着に至るまで多量の、被害者らの血液型と一致する人の血が付着していた
㋑ズボン、スポーツシャツ、半そでシャツに各々損傷があり、白半そでシャツ右肩の部分には内側からにじみ出て付着したとみられる人血(B型)が付着していた
㋒衣類は事件後一年以上経過後、昭和42年(1967)8月31日味噌出しをしていた味噌会社従業員によって発見され、前年7月20日以前、新たな仕込みが始まる前にこれらの衣類が隠されたもので、それ以降は不可能である
㋓発見場所の工場が犯行現場に近く、他に同様な事件は認められない
㋐㋑㋓だけでは、疑問の余地がないほどの証明にはならず、ねつ造の可能性を否定できない。㋒は認定の誤り。犯行着衣であるとするにはどれも疑問だらけで、認定のための必要な証拠や事実が存在しない。こんな虚ろな証拠での死刑判決は無理筋もいいところです。
静岡地裁再審開始決定(2014.3.27)の判断
・5点の衣類はDNA鑑定によって袴田の着衣でもなく、犯行着衣でもない蓋然性がある
・味噌漬け実験の結果、衣類の色合いや、血痕の色は1年以上味噌に漬かっていたとするには不自然で、ごく短時間でも、発見された当時と同じ状態になる可能性が明らかになった。
・5点の衣類という最も重要な証拠が捜査機関によってねつ造された疑いが相当程度あり、その他にも捜査機関の違法、不当な捜査が存在し、又疑われる。国家機関が無実の個人を陥れ、45年以上にわたり身体を拘束し続けたことになり、拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する。
袴田さんの無実の叫びが、ついに裁判官に届きました。村山浩昭裁判長はその日のうちに袴田さんの刑の執行と拘置の停止を決め、袴田さんは48年ぶりに監獄から釈放されました。
東京高裁大島決定(2018.6.11)の判断
5点の衣類が①犯行時に袴田が着ていた衣類である ②袴田の物であるこの2点の認定が揺るがない限り、「無罪を言い渡すべき」明らかな証拠とは言えないそれ以外の証拠は補助的なものに過ぎない
- 本田教授の細胞選択的抽出法は一般的に確立した科学的手法とは認められず、その信用性に疑問がある
- 味噌漬け再現実験で用いた味噌とこの会社の味噌の色は異なり、比較したカラー写真は劣化退色している。判断の基礎とした写真は、5点の衣類の色合いを正確に表現したものではない。これらの写真を基に大まかな傾向や、味噌漬けの色を判断したのは不合理な判断だ。
- 5点の衣類を発見時に近接した時期に、味噌タンクの中に隠すには、従業員の協力が不可欠であるが、そのような協力を得ることは著しく困難で、捜査機関が隠匿した現実的可能性は乏しい。 (都合のいい可能性論で、ねつ造の否定にはならない)
④「はけないズボン」確定判決はズボンのサイズの認定に誤りがあるが、ウエストサイズを見る限り、袴田が本件当時はけなったとは言えない(原因はウエストサイズではない
⑤「すねの傷」袴田を全裸にでもしない限り、ズボンの下の傷の発見は困難で、逮捕時の袴田の右すねに傷がなかったとは言えない。 (裁判官の無知と非常識)

611抗議行動
弁護団の主張
特別抗告理由補充書5(2019.7.17)
検察の主張を丸写しにした偏見と思い込みの大島決定に対し、弁護団は最高裁へただちに特別抗告、その補充書を順次提出してきました。その補充書5では5点の衣類が味噌タンクに隠された時期は不明であり、高裁決定では5点の衣類がねつ造証拠である可能性を否定することができないことを明らかにしました。
高裁決定はおよそ裁判所の判断と思えないずさんな決定。裁判官のねつ造に対する強い偏見が証拠の評価を誤らせ、論理的な思考を妨げたのです。
5点の衣類が犯行着衣であるとの認定部分の重大な誤り
【5点の衣類はいつ隠されたのか?時期は不明!】
隠匿(いんとく)可能な時期は
➀1966年6月30日~7月20日
② 1967年7月25日~8月31日の間
※7月20日から翌年の7月25日までは約8トンの味噌が入れられた(タンクの体積は約8㎥)
①ならば犯人が入れた⇒犯行着衣の可能性
②ならば袴田さんは逮捕・拘留中⇒ねつ造の可能性
確定判決の概要のうち
㋐は「被害者らの血液型と一致」と言うが専務はA型、妻はB型、次女はO型、長男はAB型であり、「一致」という評価は無意味。付着していた血液のほとんどがA型で最も残酷な殺され方をした次女のO型が全く検出されないのはありえない。ねつ造の可能性が強く疑われる。
㋑も同様に衣類の損傷はねつ造の可能性を否定する根拠にはならず、ズボンや半そでシャツなどのずさんな損傷の生成は、かえってねつ造の疑いを増すばかり 。
㋒隠した時期について、確定判決は7月20日以前でそれ以降はほとんど不可能と言うがそれ自体が間違い。十分可能だった。翌年7月25日以降には味噌の取り出しが始まり、8月末にはシャベルがタンクの底に届くほどの味噌しか入っていなかったので、この会社の従業員によって、作業中にごく自然に発見されることになった。
㋓は入れられた時期とは全く無関係で、ねつ造を否定する根拠にもならない。
結局、5点の衣類がタンクに入れられた時期は確定できず、よって犯行着衣であると認定することはできない。もし発見時直前に入れられたのなら袴田さんは無関係で、ねつ造の可能性を否定できないにもかかわらず、明確に時期を特定することなく、確定判決等が犯行着衣であると認定したのは明らかな誤り。それは証拠評価の誤りではなく、犯行着衣と認定するための事実や証拠を欠いていた。『5点の衣類』は犯行着衣ではない!!
一審の高裁、最高裁の重大な誤り
「衣類が味噌タンクに1年余りも漬かっていたような状態が、一朝一夕にできるとも思わない」 (東京高裁決定)1976.5.18
「5点の衣類及び麻袋は、長期間味噌の中に漬け込まれていたものであることは明らか」 (最高裁決定)1980.11.19
弁護団による味噌漬け再現実験の結果、20分で5点の衣類の色は再現された!
高裁決定の認定の誤り
「味噌漬けの当時のカラー写真は再現性が悪く、これを基に色について論じることはできない」
東京高裁、最高裁も当時のカラー写真を基に衣類の状態を確認したもので(上記)、これを否定することは、東京高裁や最高裁の判断にも反している
弁護団による味噌漬け実験の、わずかな時間で味噌色に染めることができるという事実に対して、カラー写真が劣化退色しているとか、当時の赤味噌の色が薄かったなどいうのは単なるケチ付けに過ぎない。
確定判決の証拠構造は空洞!
確定判決の「5点の衣類は犯行着衣であり、袴田さんの物である」という認定は、そのために必要な事実や証拠が存在せず、5点の衣類が味噌タンクに入れられた時期もあいまいで、合理的な疑問が山積。刑事訴訟法で言う適正手続きに反しています。ねつ造の可能性を否定できないにもかかわらず、犯行着衣であると認めたことは誤りであった。確定判決等の証拠構造は、ぜい弱であるという以上に有罪認定を支えるべき証拠の柱がない空洞構造であった
最後に、裁判所の立場で考えたとしても、公正な裁判が行われたとは言えないことを明らかにしておかねばなりません。たとえ本田教授によるDNA鑑定の手法が否定されたからといって、衣類に付着した血痕が袴田さんの物でも被害者らの物でもあるとされたわけではないのです。同様に、味噌漬け実験報告書が排斥されたからといって、衣類が長期間味噌漬けになっていたと証明されたわけではありません。それらのことから帰結される結論は、グレーだということ。5点の衣類が袴田さんのものかどうかは、分からないということでしかないのです。とすると、結論は再審開始決定が相応しい。再審を開いて、そこで再度の審理を始める決定を出すのが相当でした。
高裁大島決定は偏見と思い込みに頼って、安易に5点の衣類が犯行着衣ではない可能性を否定した。静岡地裁の再審開始決定がねつ造の可能性を指摘した以上、大島裁判長は予断と偏見を排し、ねつ造ではない証拠を明示しなければならなかった。
清水一人